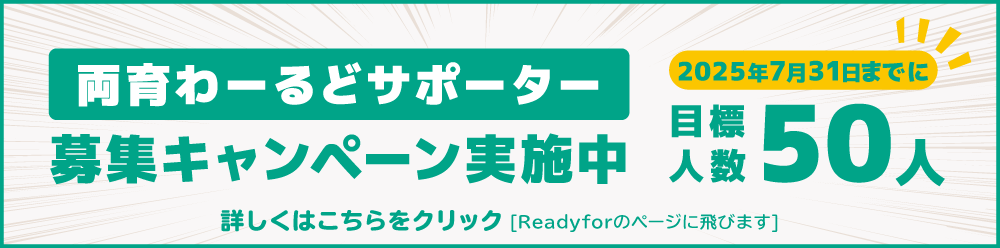両育わーるどの活動について
非営利組織の皆様には1式3万円で販売しております。法人の皆様は、お問い合わせフォームからポスター購入希望の旨、ご連絡頂けたら幸いです。
ボランティアとしてご支援を検討されているとのことありがとうございます。両育わーるどはたくさんのボランティアの方々のお力を借りて活動を行っています。ボランティアについては、募集状況が都度異なるためこちらのフォームより詳細をお問い合わせください。
取材・講演
両育わーるどに興味を持ってくださり、ありがとうございます。取材のご依頼は、こちらのフォームよりお問い合わせください。
両育わーるどに興味を持ってくださり、ありがとうございます。講演のご依頼は、こちらのフォームよりお問い合わせください。
毎月の寄付について
毎月の寄付額を変更する場合は、お手数をおかけしますが、一度支援を解約していただき、ご希望の寄付額のコースを選び改めてご支援ください。支援の解約方法は、こちらをご覧ください。
毎月の寄付を一時的に中止する場合はお手数をおかけしますが、一度支援を解約していただき、再度ご支援いただけるようになりましたら改めてご支援の登録をお願いいたします。支援の解約方法は、こちらをご覧ください。
毎月のご寄付では現在クレジットカードのご利用が可能です。詳細はこちらをご覧ください。
月々500円からご支援いただくことが可能です。
初回ご支援時に1回目の決済が行われ、翌月以降は毎月10日に決済が行われます。詳細はこちらをご覧ください。
マンスリーサポーター様へは年に一度、年次活動報告書(PDF)をメールにて送付しております。またHP、各種SNSにて日々の活動を発信しております。
またこちらに最新版を掲載していますのでぜひご覧ください。
領収書希望の旨、お問い合わせください。
今回の寄付について
つながる募金または銀振り込みによりご支援いただくことが可能です。詳細はこちらをご覧ください。
ご寄付の方法によって異なります。つながる募金は1口/100円から、銀行振り込みでは1口/3000円からご支援いただくことが可能です。
ご連絡先をお教えいただいた方に年に一度、年次活動報告書(PDF)をメールにて送付しております。
またこちらに最新版を掲載していますのでぜひご覧ください。
領収書希望の旨、お問い合わせください。
法人の寄付について
領収書希望の旨、お問い合わせください。
ご相談を承ります。オンライン会議ツール等を使ったお打ち合わせも可能です。お問い合わせフォームからご相談ください。

![難病者の社会参加白書2025〜RDワーカーの可能性〜[暫定版]公開しました!](/wp-content/uploads/2025/07/bnr-hakusho.png)